CIAL代表兼デザイナー・戸塚佑太さん、ブランドエディター・加藤大雅さんが聞きたい、「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」
CIAL代表兼デザイナー・戸塚佑太さん、ブランドエディター・加藤大雅さんによる、「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」の中間報告

「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」を問いに掲げ、この4月から継続的にインタビューを行っているCIALの戸塚佑太さんと加藤大雅さん。本プロジェクトのアウトプットとして、福岡の焼酎メーカー「天盃」とともに、コーヒーリキュールを開発することが決まったCIALは、これまでのインタビューを通じて何を考え、この先にどんな展開を見据えているのでしょうか。先日、第3期インタビュアー3組と、各担当編集・ライターの面々が一同に会して行われたオンライン中間報告会で、CIALのPRエディターとして本プロジェクトをサポートしてくれているイノウマサヒロさんが、戸塚さん、加藤さんに行ったインタビューの内容をお届けします。
CIALでは、「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」をカンバセーションズでの問いに掲げていますが、この背景にある思いについて改めて聞かせてください。
戸塚:CIALは、「MATERIA」というコーヒーブランドをつくるところから活動が始まったのですが、コーヒーの面白さのひとつは地域性があるところなんですね。僕らはデザインの仕事においても、地域の独自性を持った方々と積極的に仕事をしていて、地域独自の「偏り」のようなものに一貫して関心を持っています。日本全国に地域独自の文化がありますが、いまこれらはどんどん失われていっているんですよね。そうした状況がとても悲しくて、どうすればその地域だからこそ生み出せるものをつくり続けていけるのかという問題意識が、今回の問いの発端になっています。
加藤:CIALとしてデザインの力をいかに使っていくのかということを考えた時に、地域独自のものを伝える支援をしていきたいというのがあるんです。今回のカンバセーションズのプロジェクトには、ナオライの三宅(紘一郎)さん、ITONAMIの山脇(耀平)さんというブランドやメーカーの立場でものづくりをしている方たちが参加していますが、一方でCIALは、そうした事業主の方たちをデザインの面からサポートするような仕事をしてきました。今回の問いを立てるにあたっても、地域でものづくりをしている人たちのパートナーとして、自分たちにできることを考えていこうというスタンスが前提にありました。
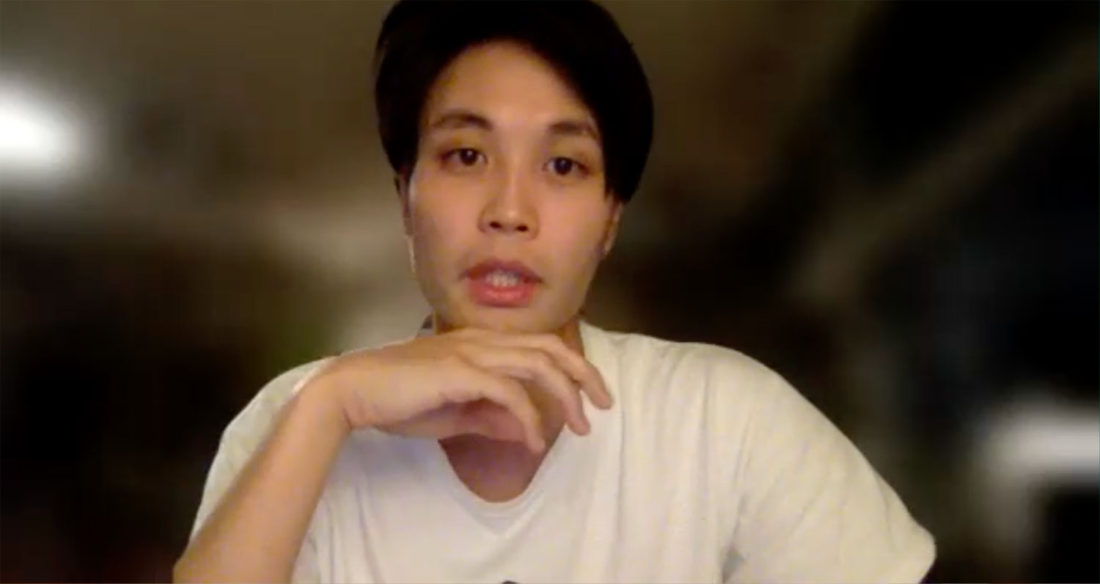
最初の取材では、デザインユニット・KIGIの植原亮輔さん、渡邉良重さんにインタビューしましたが、まずはここから振り返って頂けますか?
戸塚:もともとKIGIのファンだったこともあり、とても緊張しました(笑)。デザイナーとして地域に関わると、何かをつくってお渡しした後は、地域の人たちを信じて使ってもらうしかないところがあって、もっと踏み込んでものづくりを続けるようなことはできないかと以前から考えていました。KIGIはデザイン会社として、地域の職人さんたちと一緒にKIKOFというプロジェクトを立ち上げ、自分たちも事業主の一員としてお金の管理から店舗の運営、商品の販売までを担っています。おふたりからお話を伺って、同じ意志を持つ人たちでリスクを持ち合い、プロジェクトを続けていくことの大切さを感じました。また、先方に了承された提案を帰りの新幹線の中で考え直し、「本当に続いていくものは何か?」という観点から新たに提案をし直したという話は、自分にとって非常にセンセーショナルでした。

次にインタビューしたのは、富山のワイナリー・セイズファームのディレクターを務める飯田健児さんでした。飯田さんは、地域の中からデザインの力を使ってブランドを発信したり、ワイン文化を地域に浸透させるということをされていましたね。
加藤:そうですね。僕は昨年何度か氷見に行く機会があり、セイズファームを訪れたのですが、そこで提供されるワインや料理とのマリアージュに感動し、さらにワイナリーとしての世界観も統一されていて凄いと感じました。一体どんな人がここまでワイナリーを発展させてきたのかということに興味があったので、立ち上げから10数年にわたってディレクターを務めている飯田さんにお話が聞けてとても良かったです。飯田さんは地域に根ざし、デザインの力を使いながら活動をしていくというスタンスが一貫していましたし、自分たちの信念と客観的な視線を常に併せ持っている方でした。タイポグラフィだけのエチケット(ラベル)を一貫して変えていないという話も印象に残っていますし、自分たちの美意識とワイナリーの継続性という非常に難しいバランスを保ちながら、事業を成功させていることが素晴らしいと感じました。
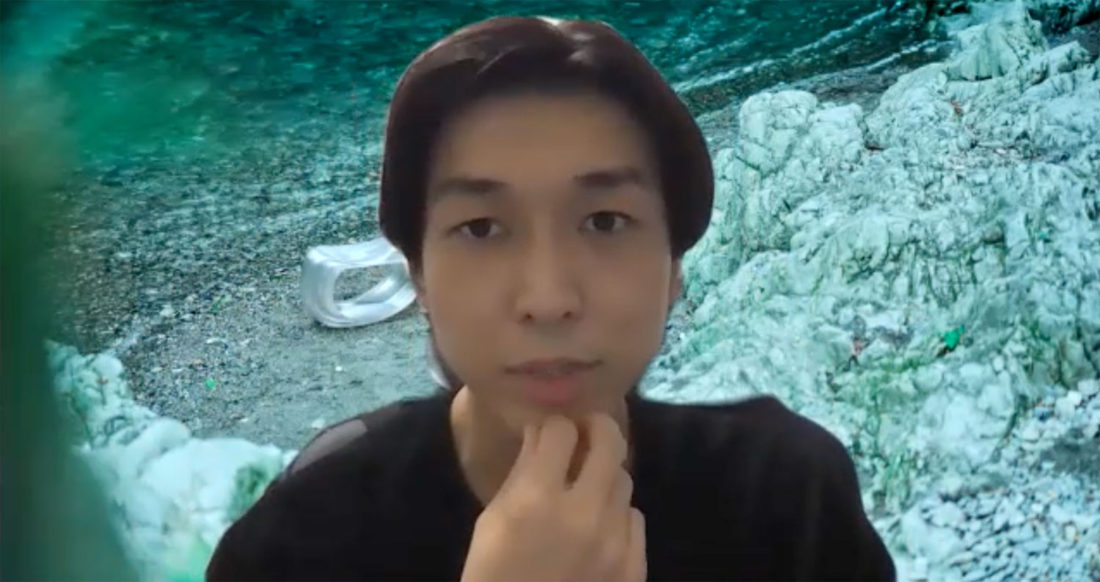
そして、これからコーヒーリキュールを共につくることになる天盃の5代目・多田匠さんへのインタビューはどうでしたか?
戸塚:何かが長く続いていくためには、時代とともに変わらなくてはいけないものがある一方で、受け継がれていくものもあります。その中で多田さんは何を続け、何を変えたいと考えているのかということをお聞きしたいと思っていました。インタビューを通じて、多田さんは売上や規模ではなく、酒蔵としての営み自体を次世代に継承していくことを大切にされていることがわかりました。成長や効率性が正義になりがちな時代の中で、そうした意思や姿勢は非常に尊いものだと感じましたし、やはり僕たちはそうした明るい意思を持ったものづくりだけをしていきたいと改めて思った取材でした。
加藤:事業が続いていくためには後継者の存在が欠かせませんが、多田さんの場合は、子どもの頃から酒蔵の中で日々を過ごし、酒造りの営みに触れながら育つ中で、継ぐという選択肢が当たり前のようにあったんですよね。その中で、父から子へ自然にバトンが渡されている感じがとても印象的でした。僕はブランドエディターという立場で、ブランドのリサーチやコンセプトメイキングなどを担当していますが、100年以上続いている天盃と、始めてから3年ほどしか経っていないCIALが、いかに視点や意思、姿勢を重ねていけるのかというところをしっかり考えていきたいなと思いました。

先日、CIALのメンバーとライターの菊池百合子さんで天盃の酒蔵に見学に行き、匠さんのお父さんである4代目の格さんにもお話を伺いました。こうした経験を通じて、CIALとしての問いにも少しずつ変化があるように思いますが、最後に今後の意気込みを聞かせてください。
加藤:当初CIALでは、事業主体者のパートナーとなって、ものづくりをサポートしていくことをカンバセーションズのアウトプットとして想定していました。でも、天盃さんとつくることになるコーヒーリキュールは、自分たちのプロダクトとしてリリースすることになりそうなので、天盃さんの文化や歴史も大切にしながら、CIALとしてつくりたいものは何か、続けていきたいと思えるものは何かということを、自分たち自身に問わなくてはいけないなと思っているところです。これまでとは異なる感覚で取り組む必要があるのでおそらく苦しむことになると思いますが、同期のインタビュアーの方々にも相談しながら進んでいけるとうれしいです。
戸塚:加藤も話したように、CIALはこれまでデザインの力を使って他者の意思や思いを形にするということに向き合ってきましたが、今回は自分たち自身が何をつくるのかというところから始めてみたいと思っています。それを起点に、地域の中でものづくりを続けてきた天盃さんたちとの関わり方や、プロダクトのつくり方を考えていきたいです。いよいよここからが本格的なものづくりのフェーズになるので、ますますがんばっていきたいですね。



