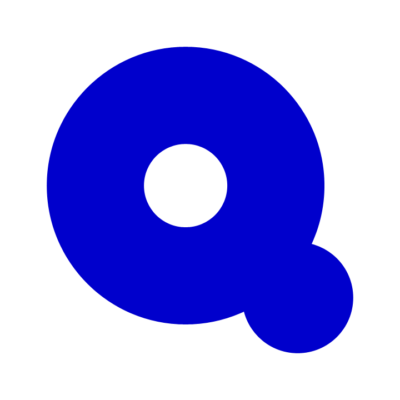CIAL代表兼デザイナー・戸塚佑太さん、ブランドエディター・加藤大雅さんが聞きたい、「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」
CIAL代表兼デザイナー・戸塚佑太さん、ブランドエディター・加藤大雅さんが、
「地域独自の食文化を、“自続”可能な形にするデザイン」について聞きたい理由

CIALは、デザイン事業とコーヒー事業を両輪に、デザイナーやエディター、焙煎士などさまざまな職能を持つスペシャリストたちが集うクリエイティブチームです。企業やブランドのアイデンティティデザインを軸に、Webやグラフィック、空間などのアートディレクションを行う傍ら、日常のシーンに寄り添うコーヒーブランド「MATERIA」の企画・製造・販売を手がけるというユニークな事業を展開しています。そんなCIALから今回インタビュアーを務めてくれるのは、代表兼デザイナーの戸塚佑太さんと、企業やブランドのヴィジョン・ミッションの言語化などを担うブランドエディターの加藤大雅さんのふたり。日本各地で育まれてきた独自の食の文化を“自続”可能な形にアップデートすることをテーマに、パートナー企業とともに具体的な商品や事業の開発を見据え、インタビューを続けていきます。
まずは、CIALが生まれたきっかけを教えてください。
戸塚:僕は20歳の頃にアフリカのウガンダに1年ほど滞在したのですが、ホームステイ先がたまたまコーヒー農家さんだったことがきっかけで、コーヒーに関心を持つようになりました。農作物としてのコーヒーを栽培して生計を立てている人たちや、彼らを取り巻くネガポジ含んだ環境、コーヒーを嗜好品として楽しんでいる人たち、それぞれの関係に興味を抱いたんです。そして、帰国後に焙煎の勉強をして、東京の高円寺でColored Life Coffeeというコーヒースタンドを開業したことが、CIALが生まれるきっかけになりました。
最初はコーヒーからスタートしたのですね。
戸塚:はい。ただ、店舗業務が忙しく、当初からやりたかったウガンダなどの産地の素材を使ったコーヒーをつくるということになかなか向き合えませんでした。そこで、商品づくりに力を入れるためにMATERIA(マテリア)というコーヒーブランドを立ち上げ、やがてお店の方はクローズしました。MATERIAは、普段PCと向き合って仕事をしているような人たちが休憩時に飲むコーヒーというのをコンセプトにしているのですが、このブランドをつくっていくプロセスがとても面白かったんです。これをきっかけに、素材の価値を高め、多くの人に愛してもらったり、楽しんでもらえるようなブランドをつくっていくことを生業にしたいと考えるようになり、やがてインドネシアにカカオ農園を持つ企業のお菓子ブランドや、信州りんごを使ったグラノーラのブランドをつくる仕事などをさせてもらうようになりました。
加藤:2020年6月にCIALのCIを自社でリニューアルしたのですが、その時に「思想・哲学が力になる世の中へ」というヴィジョンを策定しました。現代社会においては、お金や権威というものが大きな力を持っていますが、僕たちは個人の思いや考えがもっと力を持ち、経済的にも継続していけるような状況をつくりたいという思いがあります。それを実践していく最初の一歩として、まずは自社CIのリニューアルを通じて自分たちの思想・哲学をしっかり定義し、ヴィジュアルや言葉などさまざまなものに転換していくということを行いました。今後も自分たち自身がものづくりに関わりながら、ブランドや企業の思想を定義し、それをさまざまな視覚表現や体験に落とし込んでいくことで世界観を広げるお手伝いをしていきたいと考えています。


現在のCIALにはどんなメンバーが集まっているのですか?
加藤:集まっているメンバーは多種多様で、大きくふたつのチームに分かれます。デザインチームには、ビジュアル側を担うデザイナー、企業のヴィジョン・ミッションなどを言葉で定義していくブランドエディター、広報活動を担うPRエディターらが集まり、一方のコーヒーチームには、焙煎視やバリスタ、ソムリエなどがいます。もともとColored Life Coffeeに客として通っていた自分を含めて、当時のお店に集まっていた5名くらいがコアメンバーになっていますが、現在のコミットの仕方はそれぞれで、戸塚以外の面々は他の仕事もしながらCIALに関わっています。
デザイン事業とコーヒー事業を並行していることの意味についてはどう考えていますか?
戸塚:デザイン事業で僕らが関わる企業やブランドは、自分たちでリスクを負って事業を行っています。そういう方たちと仕事をするにあたって、自分たち自身が商品やブランドをつくったり、リスクを負って事業を運営しているということは非常に大きな意味を持ちますし、より純度の高いコミュニケーションができると考えています。一方のコーヒー事業側から見ても、自分たちの事業の思想やコンセプトの言語化、商品の展開アプローチなどをブランディングチームとともに考えられることは大きな強みになります。


加藤:基本的に僕らのデザイン事業というのは、クライアントから仕事を依頼され、納品をしてフィーを頂く仕事です。そして、CIALには、アイデンティティデザインに始まり、できるだけ長い目線で企業やブランドの活動を支援していきたいという考えがあります。これは、デザインの価値が認められている東京などであればビジネスとしても成立しますが、それ以外の多くの地域においては持続可能なモデルになりにくいと思っています。こうした地域において企業やブランドと長期的に関わっていくためには、受注発注の関係からさらに踏み込み、CIALとしてもリスクを取る必要がある。だからこそ、自社でコーヒーを事業として回していく経験を通じて、事業会社としての視点を養うことが大切だと考えています。
戸塚:例えば、生産者側と共同出資してブランドをつくるなど、今後はデザイン事業においても自分たちがリスクを取りながら、パートナーと継続的な関係を築いていけるようなプロジェクトを増やしていきたいと考えています。僕は、CIALを始める前にIT関連のスタートアップの立ち上げに関わっていたのですが、多くのスタートアップは上場を掲げて資金を調達し、企業をひたすら成長させて、最終的には株式を売却することを目標に掲げます。それ自体を否定する気はありませんが、自分たちが目指したいのは資金を調達し、上場を見据えて「成長」していくことではなく、それぞれの地域で育まれてきた文化や風土、記憶の堆積のようなものが経済的に“自続”していく状況をつくっていくこと。だからこそ、デザイン事業で得た資金をエンジンに、コーヒー事業などで新しい試みを行っていくという関係性が大切だと考えています。

今回のカンバセーションズの企画では、 「アフターコロナ時代のものづくりや、ブランド/メーカーのあり方」という共通のテーマのもと、3組のメンバーがインタビューを行っていく予定ですが、CIALとして設定したい「問い」についてもお聞かせください。
加藤:「地域に根ざす食の文化が、これからも続いていくためには何が必要か?」ということについて考えていきたいと思っています。自分たちは、人口や経済が縮小していく日本社会の中で、地域ごとにある偏りのようなものがこれからも残ってほしいと考えています。仮に経済的な成長を目指すのであれば、東京や海外に出ることが最も速いかもしれませんが、地域に行けば行くほど独自の文化があり、その中で育まれてきたものには特有の温かみや豊かさがあります。今回のプロジェクトでは、これまでも自分たちが向き合ってきた「食」にフォーカスしたいと思っているのですが、「食」というのは人々の日常を形づくっているものだからこそ、長い時間をかけて育まれてきた地域の大切な文化になっていることが多いんです。例えば、僕が大学生活を送った秋田には、きりたんぽやバター餅、ババヘラなどのユニークな食文化が残っています。人口減少や食の画一化などによって地域独自の食文化の存続が危ぶまれている中で、これらを残していくためには何が必要なのかということを考えていきたいと思っています。
戸塚:こうした「問い」について自分たちだけではなく、パートナーとなる生産者や職人さん、あるいはブランド、企業と一緒に考えていきたいです。いままさにパートナーとなる企業と話を進めているところなのですが、その方たちと一緒に具体的なアウトプットを見据えながらこの問いと向き合い、その中でCIALとしてできることについても考えていければと思っています。地域の文化を担っている当事者側からすると、東京からやってきた自分たちのような人間に新しい商品やブランドをつくると言われても、「何を偉そうに」と思われる部分が少なからずあるはずです。とはいえ、地域のユニークな文化の中には、いまの形のままでは続いていかない、もったいないと感じてしまう部分が多いことも事実です。こうした葛藤がある中で、地域の生産者やブランドといかに良い関係性を築いていけるのかということを考えることも、自分たちにとっては大きな糧になると思っています。

具体的にはどんな人たちにインタビューをしていきたいと考えていますか?
加藤:まずは、先ほど戸塚も話していたように、単に発注されてデザインをするだけではなく、自分たちもリスクを負いながら生産者側と継続的な関係を築き、地域独自の文化を現代にアップデートしていくようなことに取り組んでいるデザイン側の方にお話を伺ってみたいですね。他にも、日本ならではの食の価値をアップデートしようとしている企業やブランドに携わっている方、地域独自の食文化を流通させるプラットフォームやメディアなどの事業を展開しているような人にもお話が聞けると良いなと思っています。
最後に、今回のプロジェクトの抱負をお聞かせください。
戸塚:地域で生まれたモノや文化がどんどんなくなっている現状はとても悲しいですし、これから消えゆく危機にある各地の文化や風土は本当にたくさんあると感じています。今回、カンバセーションズという枠組みを通してこうした課題と向き合い、自分たちの「問い」を何かしらの形でアウトプットしていく機会を与えてくださったことをとてもありがたく思っています。自分たちが素敵だと思う取り組みをされている方々が、僕たちが投げかける「問い」に対してどう応えてくれるのかということも、いまからとても楽しみですね。
加藤:日本各地でユニークな活動をされている方や、CIALが掲げる「思想・哲学が力になる」ということを体現されているような方たちにお話を聞けることがとても楽しみです。インタビューでは、単に先方の活動について伺うだけではなく、CIALが仮説を持って取り組んできたことや、これまで考えてきたこともしっかりぶつけてみたいです。そうすることで他のメディアなどではあまり見られなかった反応や言葉というものが記事になって発信されていくと面白いなと思っています。