ナオライ代表取締役・三宅紘一郎さんが聞きたい、「自然から感謝されるメーカーのあり方」
ナオライ代表取締役・三宅紘一郎さんが、
ようび建築設計室 室長・大島奈緒子さんに聞く、「生態系の一部として生きる私たちにできること」

日本酒業界の再生を目指して、広島県呉市の久比/三角島を拠点に「MIKADOLEMON」「浄酎」「琥珀浄酎」という革新的なお酒を開発・販売するナオライ。代表取締役の三宅紘一郎さんは、「三方良し(売り手・買い手・社会)」の考え方に自然と未来への配慮も加えた「五方良し」の誰も搾取されないビジネスモデルを描きながら、「自然から感謝されるメーカーのあり方」を問い続けています。今回インタビューするのは、ようび建築設計室の大島奈緒子さん。岡山県西粟倉村で家具製作や建築・まちづくり事業に取り組みながら「西粟倉村むらまるごと研究所」の代表理事も務める大島さんに、自然の中で生きている感覚や、組織運営・事業運営の秘訣について聞きました。
Text:米山凱一郎


ナオライは、この40年で酒蔵数が約3分の1にまで減少している日本酒業界の再生を目指して2015年に創業した会社です。広島県呉市にある瀬戸内の離島・三角島(みかどしま)に本社に置き、島で育つ無農薬レモンと純米大吟醸をかけ合わせたスパークリング日本酒「MIKADO LEMON」をつくっており、また、神石高原町では日本酒からアルコールだけを抽出したウイスキーのようなお酒「浄酎」、そこにレモンをかけ合わせた「琥珀浄酎」を製造、販売しています。これらのお酒造りを進める中で自分たちでも有機農業に取り組み始めた私たちは、見えないところでたくさんの命が生きていることを知り、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三方良しに「自然良し」と「未来良し」を足した「誰も搾取されないビジネスモデル」を思い描くようになりました。そして、そんな「自然から感謝されるメーカー」として思い浮かんだのが、ようび建築設計室の大島さんだったんです。まずは改めて、ようび建築設計室や大島さんご自身について聞かせていただけますか?
大島:ようびは、広島県のお隣、岡山県の西粟倉村という人口およそ1400人の村で事業を展開する、家具や建築の会社です。西粟倉村は面積のほとんどが山で、ようびは人工林として多く生えているヒノキを主な材料としています。ヒノキというと花粉症などネガティブな話が多くなってしまいますが、もともとは私たちの先祖のみなさんが良かれと思って一生懸命植えてくださったものなので、私たちはそれを感謝して受け取って未来につなげたいと思い、10年前から家具づくりをはじめました。また、家具をつくるうちにインテリアのご相談もいただくようになったことをきっかけに建築や内装の部門を私が立ち上げました。


事業において大切にしていることは何ですか?
大島:「人がつくる」ことと、「人とつくる」ことですね。これからは人がつくらなくても良いものがどんどん増えていくからこそ、「誰と何をつくるか」が非常に大事になると思っています。実は、ようびの工房は2016年に一度大火事で焼けてしまったのですが、再興を目指した「ツギテプロジェクト」では全国から600名近くの方が応援に来てくださり、杉の木を5500本組み上げて新社屋を建てることができたんです。人口1400人しかいない村で、いろんな人の力を借りながら設計から施工までみんなの手で完成させられた経験は、私たちにとってとても大きな財産になっています。
それは大変なご経験でしたね。火事が起きてしまったところで立ち止まらずに、すぐに行動を起こすには相当のエネルギーが必要だったのではないかと想像します。
大島:あの時、私たちを支えてくれたのは、代表の大島(正幸)が言った「微力は無力じゃない」という言葉です。ツギテプロジェクトは誰一人欠けても達成できませんでしたし、本当にしんどい時に知人から届いたメッセージに救われたこともありました。ものをつくる時や未来のことを考える時に、「何をやっても無駄」と思ってしまうことが一番しんどいことだと思うので、一日一分だけでも良い方向に考えてみるとそれだけで微力は無力ではなくなり、世の中が変わっていくと思うんです。


私も以前ようびさんの新しいオフィスに伺わせていただいたのですが、田んぼのど真ん中にぽつんとあるその存在感に圧倒された記憶があります。このオフィスにはどのようなコンセプトがあるのでしょうか?
大島:コンセプトは「自律」です。森や林業の循環と同じように、森から木を使わせていただいている私たちが生態系の中の建築として存在していくために、エネルギーを自分たちで賄う「オフグリッド=自立」まではできなくとも、やれることを一つひとつ実現しています。たとえば、事業で出てしまった廃材を再利用するための薪ボイラーを外に導入して、建物全体に床暖房をぐるりと回しています。また、オガクズは地域の牛屋さんのところに引き取っていただくことで、腐りにくい針葉樹と牛の排泄物が混ざり、発酵が早く進んでまた西粟倉の土に戻すことができています。自分たちがどれだけの薪を使っているのか、ごみを減らせているかということに自覚的でいたいですし、それによって行動を律することができればと思っています。こうやって使わせていただいた自然を、土地の循環にもう一度戻せることを凄く嬉しく思っています。




私が大島さんと初めてお会いしたのは、『The Japan Times』主催の「里山コンソーシアム」で西粟倉村や鳥取県智頭町のツアーに参加したときでした。その際、大島さんに西粟倉村のヒノキの林をご案内いただく場面があったのですが、いつもとは異なる大島さんの本気の表情がとても印象的でした。森や林に入るときは意識が変わるのですか?
大島:私が森や地球に関わる事業をしたいと思うようになった瞬間がいくつかあって、そのうちのひとつが初めて西粟倉に来た時のことでした。森に入った瞬間に、「いまこのタイミングで何かやらないと、この森はもうやばいだろう」という責任感が湧いたと同時に、森とそれまで守ってくださった方への感謝が溢れて、西粟倉に来ると決めたんです。その時の感覚はいまもずっと持っているので、森に入ると「私がやるんだ」という気持ちが蘇ってきますし、日本中が禿山だった時代に行われた植樹という行為を否定することなく、時間の流れの中の一部としての自分や、生態系の一部としての自分であることを思い出すことができます。
「生態系の一部としての自分」という感覚はとても面白いですね。ナオライがレモンを育てている瀬戸内の島々も、かつて柑橘の栽培で栄え、島中が柑橘畑であふれたことでもともとの生態系が失われてしまったようです。しかし、何もしないと雑木・雑草が増えてしまうばかりなので、人間が少しだけ手を入れるくらいがちょうど良いのかもしれないと感じています。大島さんは、いつ頃から自然へと意識が向いていたのですか?
大島:私たちは、環境破壊や公害について学び始めた世代で、特に自分はそういった書籍に触れることが好きな子供でした。ある日、環境についての授業の中で「森の木を切るのは悪いことだ」と先生が説明したので、「伐るべき木もある。もっとちゃんと説明してください」と授業後に抗議したことがありました。だいぶ面倒くさい小学生ですよね(笑)。 その後、大学では木造建築を学ぶ「木匠塾」の活動に関わるようになり、日本では木造建築を学ぶ機会が少ないことや、建築業界と森のつながりを取り戻すためにはちゃんと森のことを知る必要があることを課題に感じながら、ものづくりに取り組んでいました。

小学生の頃のエピソードはとても象徴的ですね。他にも、大島さんがどういう幼少期を過ごされたのか、親御様とのコミュニケーションも含めてお聞きしたいです。
大島:生まれは大阪で、ごく普通のサラリーマン家庭で育ちました。父も母も自然に特別興味がある人ではなかったように思いますが、幼稚園の先生がいろんな生き物に触れさせてくれる人だったので、その影響が大きかったんだと思います。飼い始めたダンゴムシを全滅させてしまったり、カタツムリを何世代も繁殖させられた記憶と経験がいまでも残っています。その頃の私は、道端の雑草を抜くことも自然破壊だと思ってたんですよね。授業で行われる自然破壊や環境汚染のディベートではもの凄く傷ついていましたし、同世代の人たちもいつかそういった行為をしてしまうのだろうかと考えてしまっていました。でも大人になってからは、雑草を抜いても良いエリアがあることが分かっただけでなく、もっと長い地球の歴史を知り、「地球に比べたら、人間ってそんなに凄くないよね」と思うようにもなりました。だからこそ、自分が何かアクションをすることへの躊躇がなくなった気がします。もちろん、絶滅してしまう種があることへの悲しみや焦燥感はいまも変わらず持っています。
身の回りのあらゆる体験から自然とのつながりを感じられていたんですね。私自身、ナオライの事業で有機農業を始めるまで、「自然を育む」「生命を生み出す」ための学びを一度も受けてこなかったということに、最近気がつきました。体験する機会も、現代はとても少ないと感じています。生態系の一部として生きていく意識や自然とつながっている感覚は、どうやったら身につけることができるのか、アドバイスがあれば教えてください。
大島:幼稚園の頃から生命に触れてきた私の経験が自然との関わりにつながっているように、やはりある程度は直接的な体験が関係すると思います。ただ、私が重要だなと思っているのは、何よりも「自分自身とつながること」です。私にとって森に行くことは、自分がいまなぜこの場所にいるかを思い出し、自分自身の根っことつながるための儀式のようなものなんですよね。自分が自分とつながっていない状態で他人とつながろうとすると負担がかかるから、一日のどこかで落ち込むタイミングがあれば、大層なことではなくて良いので何かを試してみると良いと思います。たとえば「目を瞑る」とか。自分自身とつながることができれば、何とでもつながれるようになると感じています。



西粟倉には、村おこしの事例やようびさんの活動を見るために毎年多くの方が訪れていると思います。中には、大島さんのような感覚をお持ちでない方もいらっしゃると思いますが、自然へと意識を向けてもらうために、どういうコミュニケーションを取っているのですか?
大島:私は、人を変えることはある意味諦めているというか、あまりしないようにしています。もちろん、スキルが高ければそれが可能だということは承知しているんですけど、基本的には自分が誰かのことを変えられるとは思わないようにしています。それよりも、常に自分は変われるという感覚を持つようにしています。その結果私自身が楽しめていれば、そこには常に人が入ってくると考えているんです。人にしても植物にしても、私は何かが勝手に育っていく様子を見ることに一番の喜びを感じているのかもしれません。
今日は、母親としての大島さんについてもお話を伺いたいと思っていました。大島さんには小学生の娘さんがいらっしゃいますよね。ようびさんの事業は、大人が中心の家造り、まちづくり、環境づくりではなく、子ども中心のものであると感じています。子どもたちとコミュニケーションをする上で意識されていることがあれば教えてください。
大島:「大人中心ではなく子ども中心」というのは少し違っていて、「それぞれが自己中」で良いと考えています。私自身も「私は私のやりたいことをやります」と言っていますし、娘にも「あなたのやりたいことをやってなさい」とお願いしているんです。「世界の中心は奈緒子じゃないから」と子供の頃によく親に怒られていて、 いまでもそのまま生きてしまっていますけど、隣にいる人にとっての世界の中心はあくまでもその人であって、私は脇役なんですよね。私の娘も、お腹にいる時は一緒にいてくれましたが、生まれた瞬間から彼女のストーリーが始まっていると思いながら接しています。

そのお考えは、組織運営にも通じていますか?
大島:そうですね。いろんなタイプの組織がありますが、私は「どれかひとつが正しい」とは思っておらず、必要なプロジェクトに応じていろんな形態に変化できるのが最も成熟した組織だと考えています。緊急時などは支配度を上げたり、何かを生み出したい時はフラットな関係にしたり、その両方を行き来できる組織や地域が最強だなと。一人ひとりがそれぞれの色を失う必要は全くないですし、その人らしくあるということが、他の人の色を変えることにはなりません。引いて全体を見たらひとつの色に見えることもあるかもしれませんよね。組織運営においても親子関係においても、自分は自分の色のままいたいけど、誰かの色を変えたいとは思っていないんです。
母親になられてから気付いたことはありますか?
大島:娘を出産した時に最も感動したのは、「私、哺乳類なんだ」って思えたことですね。娘が生まれてからたった一週間で「退院してください」って言われた時には、「こんなにも教えてもらえないのか」と怖かったんですが、何も習わなくてもちゃんと目は覚めるしおっぱいは出るし、脈々と流れる時間の中で自分が生きている感覚を、その時にも感じましたね。先人たちが命を紡いでくれたから私たちがいるし、私も娘を産んだことで「自分も生き物であり、最終的には土に還れる存在なんだ」とこれまで以上に思い、大きな感動がありました。また、いまの私の行動がその先の世代につながっているという責任感も生まれたように思います。
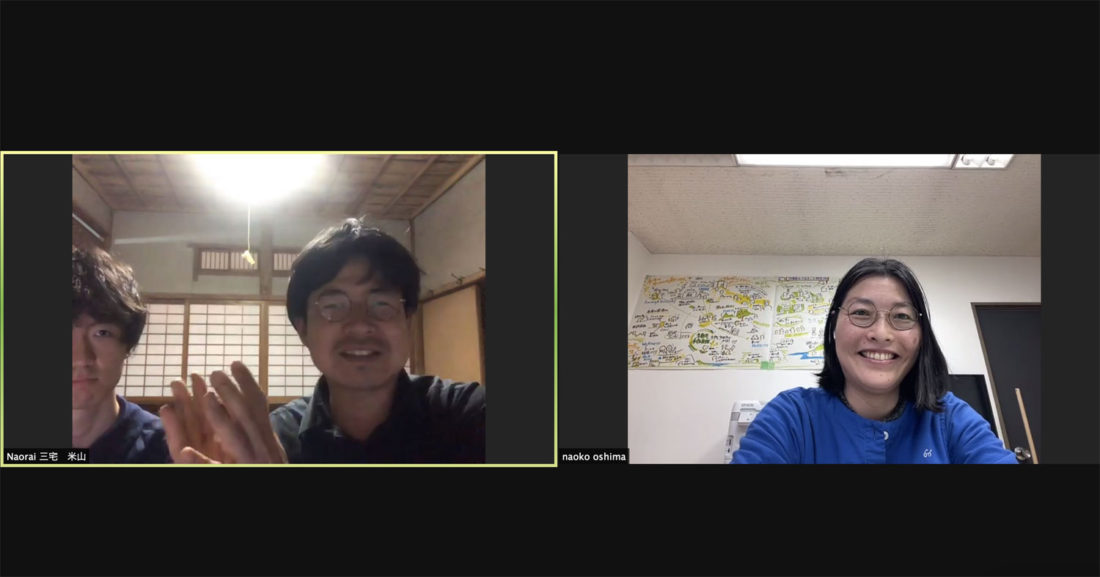


多くのヴィジョンを実現するためには、それぞれの事業を着実に広げていく必要もあると思います。そういった意味で、事業や活動に優先順位はありますか?
大島:やった方が良いことはやるしかないと思っています。もちろん、優先順位を決めることは大事ですけど、本当に大事なことは優先順位を決め、スケジュールを立てて守れるようなものではなく、「全部大事!」ってことがときどき起こるんですよね。ばーっと種をまいて、芽吹いてきたものを育てるような。そのときに踏ん張れるかどうかが、チームの明暗を分ける気がしますね。
ようびチームがこれまで踏ん張ってこられた秘訣はありますか?
大島:当番で昼ご飯をつくって、みんなで一緒に食べることだけは、ようびが立ち上がってからずっと続けてきました。困難な状況の時にちゃんと助け合えるメンバーであることが大切ですし、この習慣にチームは支えられてきたと思います。

これから西粟倉村ではどんなことが始まりますか?
大島:2020年7月に西粟倉村と一緒に立ち上げた「西粟倉むらまるごと研究所」の代表理事に就任したので、「ローカルから未来を発明していくぞ」と意気込んでいます。「生態系の本領発揮」を掲げるこの研究所では、「最新テクノロジーは地域や人を幸せにできるのか」という問いに向き合っていくことになります。人口減少や大規模な気候変動によって、おそらく地方はこれからも予測できない危機に直面していくはずですが、同時にテクノロジーの進化も素晴らしいスピードで進んでいますよね。しかし、マス向けに開発された技術が人口の少ない村には合わない可能性もあるので、自分たちに必要なものを自分たちで考え、試してみることで、未来をつくっていきたいと考えています。失敗しても良いから実証検証にどんどん取り組むことで、未来にチャレンジしていく組織になれたらと考えています。また、この「自分たち」というのは閉ざされた組織ではなく、共感してくださる人や企業などが増えていくイメージを持っています。
大島さんは自然や企業、子ども、そして自分に対して本当に誠実に向き合われてることがよく分かり、改めてようびさん・大島さんのファンになりました。本日はありがとうございました。
大島:こちらこそありがとうございました。私自身が尊敬してやまない三宅さんにそういっていただけて本当にうれしいです。日本のいろんな地域でいろんなことが起き、それぞれの地域が個性を持った状態でつながれるととっても強いなと思ってるので、これをきっかけにまた多くの方とつながれたら嬉しいです。本日はありがとうございました。




今回は、「問い」の大切を改めて感じたインタビューとなりました。これまで「問い」を意識して話をすることはあまりありませんでしたが、良い「問い」を持つ方は面白いことをやられているということを体感できました。これからもなぜその「問い」を持っているのかという部分をしっかりと深められるインタビュアーになりたいと思いました。大島さんに感謝です。

