

CINRAでは教育の事業を新たに立ち上げようとしているのですが、今日は「メディアと教育」という観点から、田中さんがこれまでにNHKで取り組まれてきた教育関連のお仕事について伺いたいと思っています。まずは、田中さんがNHKに入られた経緯からお聞かせ頂けますか?
田中:もともと僕はエンターテインメントをやりたくて、1987年にNHKに入りました。当時は毎年150人くらいディレクターを採用していた時代だったのですが、そのほとんどはドキュメンタリーなどジャーナリスティックな番組をつくりたい人たちだったんですね。僕のように歌番組をつくりたいという人間は他にいなくて、一人だけ浮いている存在でした。でも、自分にとってテレビというのはエンターテインメントだったし、当時はダウンタウンなどが出てきた時代で、お笑いなどもカルチャーとして面白いと感じていました。入局後は音楽芸能部に配属になったのですが、ここは新入社員が行くような場所ではなく、直近の先輩が10歳上という部署でした。そこで2年間下積みをした後、京都放送局勤務を経て、ハイビジョン番組をつくる部署に異動しました。そこで、インターネットなどのニューメディアに関わるようになり、まだプロバイダすらなかった90年代前半に、文字通りインターネット回線をNHKの建物に物理的に通したりということをしていました(笑)。

そうした新しいメディアを使った番組などもつくられたのですか?
田中:はい。当時、いまのSkypeに当たるような「CU-SeeMe」という遠隔コミュニケーションができるソフトウエアがあったのですが、これを使って番組をつくろうということになりました。ただ、このシステムはつながる人を自分ではコントロールする仕組みではなく、誰でも会話に入ってこられるようなもので、これを生放送で使ったところ、誰だかよくわからない人たちが世界中から集まってきました(笑)。動画でのやり取りはできたのですが、10秒おきに更新されるスライドショーを見ているような感覚で、まるで火星と交信しているような気分になったことを覚えています。
そのやり取りを生放送でしてしまうというのは、相当チャレンジングですね(笑)。
田中:インターネットがどんなものかまだしっかり理解されていない時代だったからこそ実現できたのだと思います。結局僕は、この頃と同じようなことをいまでもしているような感覚があります。インターネットにしてもそうですが、一部の人たちが手探りで始めて、そこでの経験などがベースとなって後からルールが整備されていくところがあるんですね。とにかくルールができる前のことをやるというスタンスが自分の中にはずっとあって、何が良くて何が悪いかということを自分自身で判断しながら、ルール化される以前の分野を開拓するということを続けているのだと思います。



田中さんが教育番組に携わるようになったきっかけを教えてください。
田中:先に話したハイビジョン番組の部署が解散になった後、教育のセクションに配属されたのがいまから20年前で、そこから教育関連の仕事を続けています。そこで最初に手がけたのが『わがままオーケストラ』という番組で、ラヴェルの『ボレロ』をテーマに、子どもたちが歌詞をつけたり、曲をアレンジをしたり、身体表現に変えたりする活動に取り組み、それを最後に発表するという企画でした。試写で関係者たちも思わず涙してしまうような感動的な内容になったのですが、教育番組という枠の中で、参加した子どもたち、視聴者、そしてスタッフが全員ハッピーになれるようなものをつくることができ、とても面白い仕事でしたね。

いまでこそ子どもたちが音楽やアートに触れるにあたって、体験化、身体化をしていくようなアプローチは増えていますが、当時はまだそういうものはあまりなかったのではないですか?
田中:そうですね。当時は、授業で使うための音楽教育番組しかなかったのですが、そうではないものをつくりたいという思いがありました。その後に手がけた『マテマティカ』という小学校低学年向けの算数の番組も同じような視点でつくったものです。算数の授業では、三角形のことを3つの点を直線で結んだ時にできる図形と教わりますが、実際の子どもたちはそのような視点で世界を見ているわけではないですよね。そこでこの番組では、例えば円を書く方法として、木の棒に紐でつながれた牛が足元の草を食べながら歩き続けたら、草がなくなったところに円ができるのではないかということを実証したり、自分で操作できる数学的原理のようなものを映像化するということを試みました。同じ考え方で、カラスを木の棒に結びつけたら逃げようとする軌跡で球体ができるというアイデアもあったのですが、円と球というのは学校教育のカリキュラム的にはまったく違うフェーズなので、一緒に扱ってはいけないと注意されたりもしました。学校では、平面図形を学んでから立体図形に進むんです。でも、子どもの視点に立てば、身の回りにあるものは立体で、そちらの方が自然なんですけどね。
その辺は、教育のシステムが画一的である以上、どうしてもぶつかってしまう問題ですね。
田中:社会システムとして教育があることはもちろん悪いことではないですが、すべてを盲信してしまうのは良くないと思うんですね。学校の先生の中には面白いことをしている人たちもいて、例えば、10進法を学ぶにあたって、自分たちで記数法を考えるという授業をしている方なんかもいるんです。そうすると子どもたちは、「この飾りをつけたら桁が上がったことにする」などのルールを独自につくって、10進法に代わる記数法の表を壁一面に貼ったりする。そういう光景を見ていると、子どもたちには何でもできる気がしてくるし、この経験をした子は記数法のことを絶対に忘れないですよね。自分で原理を編み出したり、ものをつくるマインドで物事を見た方が人生は圧倒的に豊かになるはずですし、それは決して難しいことではなく、誰にでもできることなのだと思っています。



自分で原理から考えていく体験を促したり、発見の場をつくっていくというのはある種のファシリテーションですよね。その引き出しというのは、音楽や算数など分野ごとにある程度異なるとは思いますが、それらをすべて横断するようなアプローチができると素晴らしいですよね。
田中:ある種の全人教育のような話になってくると思うのですが、そういうことができたらいいなと考えてつくったのが『未来への教室』という番組でした。これは、世界の一流の人物が現地の子どもたちに生涯に一度の特別授業を行うというテーマのもと、数日間かけて行うワークショップの過程を記録していく番組でした。例えば、絵本作家のエリック・カールさんの回では、ご本人と打ち合わせをする中で、代表作である『はらぺこあおむし』の「本に穴を開ける」という画期的なアイデアに着目し、穴を開けることから想像力を膨らませていくようなワークショップを行いました。

田中さんは現在「日本賞」という教育番組の国際賞の事務局長もされていらっしゃいますよね。その中で、教育番組におけるワールドスタンダードの変化などについて感じることがあれば教えてください。
田中:最近は、社会課題を取り上げたドキュメンタリー番組などが非常に増えています。かつては、教育イコール学校などの教育機関という考え方がありましたが、多様化する社会の中で現在はまったく異なる領域の人たちが教育的な価値を含む作品をつくっています。例えば、今年も「BLUE」という海洋汚染を描いた作品がエントリーし、高い評価を受けました。以前はこういうコンテンツが日本賞にエントリされることはなかったのですが、最近はこうした切り口の作品が増えていて、教育の定義が広がっていることを感じています。また、特にヨーロッパの教育番組制作者の間には、社会的に発言力が弱い子どもたちに発言の機会を与えることこそ教育番組の使命であるという、「GIVING THE VOICE」の考え方が昔から浸透しているのですが、日本の教育番組はあまりそうした視点ではつくられておらず、こうした文化や社会的習慣の違いが番組制作にも影響を与えています。
文化や価値観が地域によって異なる中で、日本賞の審査員の間では何かコモンセンスのようなものはあるのですか?
田中:コモンセンスというより、むしろ共通の価値を見出すためにバトルをしてくださいと伝えています。審査員はヨーロッパ、アジア、中南米などさまざまな地域から来ているので、当然価値観は違います。その中でお願いしているのは、相手の価値観をリスペクトしてほしいということだけです。また、作品そのものの優劣ではなく、「Educational Value」(=教育的価値)を最終的な判断基準にしていて、見た人の行動に変化をもたらすような作品かどうかというところを最重要視しています。教育的価値を考える上で社会的な影響力はもちろん重要ですが、同時に欠かせないのは継続性です。いま3歳の子供に教育を与えるのであれば、その子が5歳、10歳、そして大人になる時まで責任を持てるか、継続的に教育的な効果が保てるかということが大切だと思っています。



日本の教育における課題についてはどのように考えていますか?
田中:以前に、伊藤穰一さんの妹さんで、アメリカの大学で教育などについて研究されている伊藤瑞子さんが、「FIHSHING THE POD」という言葉を使われていたんですね。簡単に言うと、自分のメンターになるような人が簡単に釣れる池があると良いという話だったのですが、例えばチェスに興味を持った時に、最高の名人というのはその辺に歩いているわけではないですし、自分で連絡を取って会いに行くということも子供には難しいですよね。いまの日本には、この「FIHSHING THE POD」のような環境が少ないことが課題だと思っていて、いま我々が取り組んでいる『プロフェッショナル子ども大学』では、さまざまなプロフェッショナルが集まっている池をつくるようなことができるといいなと漠然と考えています。

僕の課題意識は、子供が夢中になれるものを見つける環境が減ってきているということにあります。例えば、音楽を好きになるきっかけが、これまでであれば親戚のおじちゃんが聴かせてくれたCDだったりしたと思うのですが、インターネットで探したい情報が簡単に検索できる時代になって、こうした血縁、地縁のコミュニティなど学校教育とは異なる文脈での出会いやセレンディピティが少なくなっていると感じています。こうしたきっかけの部分と、それを見つけた後に深めていける機能がおそらく両方必要なんだろうなと思います。
田中:そうですね。もうひとつ僕が感じているのは、アウトプットの機会をもっと増やした方がいいということです。メディアの仕事をしていて感じることですが、アウトプットをするためには、たくさんのインプットが必要なんですよね。勉強ばかりしていてアウトプットが少ないと、結果的にインプットの質が悪くなってしまう。例えば、複数の学年が一緒に授業をする複式学級の場合、上の子が下の子を教える機会もあって、これも立派なアウトプットですよね。実際にそれによって教える子の学力も上がったりするし、もっと子どもたちが自由にアウトプットできて、フィードバックを得られるような環境を日常の中でつくっていくことも大切だと感じています。
最後に、メディアの立場から教育に関わることの意義についてもお聞きしたいと思います。例えば、学校教育の現場では先生一人に対して生徒が数十人という関係性がベースになっていますが、より多くの人たちへのアクセシビリティがあることがメディアのひとつの強みだと思っていて、NHKのようなメディアには、経済格差や地域格差という教育における大きな課題を乗り越えられるアドバンテージがあるように感じています。
田中:日常的な教育コンテンツにおいては、オンラインへの移行がますます進んでいくと思いますが、我々放送メディアということで考えると、問題提起という部分で力が発揮できるのではないかと考えています。また、以前に一隻の船に子どもたちが乗り込み、共同生活をしながら地球環境について学ぶ『未来への航海』という番組をつくったのですが、こうした非日常がデザインできることもテレビなどメディアの力だと感じています。社会の現実そのものから直接何かを学んでいくことは従来の教育システムの中ではなかなか難しく、こうしたアプローチも、地域や空間、人などさまざまなものをつないでいけるメディアが教育に関わる際のひとつの切り口になるのかもしれないですね。
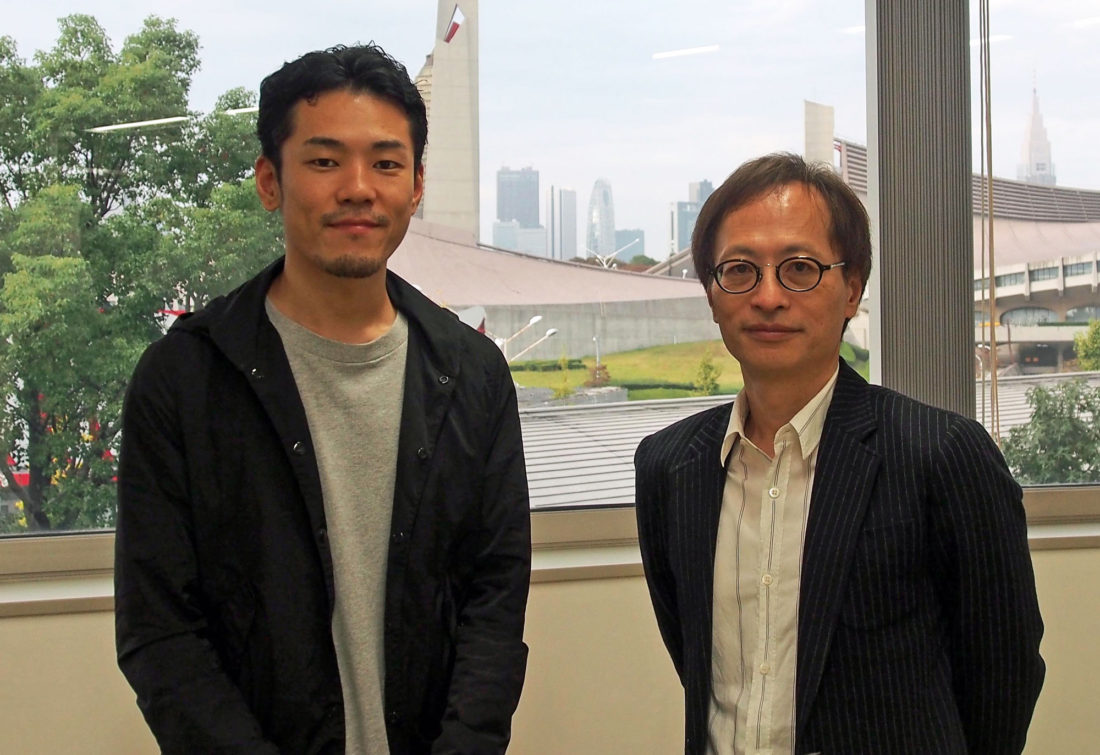


田中さんのおっしゃる通り、メディアは、長時間にわたって顔の見える個人を相手にするものではない一方で、「問題提起」もしくは「発見」のようなものを強力に、広範囲に促すことができる装置なのだと思います。その力をどのようにしてサービス設計に埋め込んでいくか、ヒントを頂けたお話でした。


