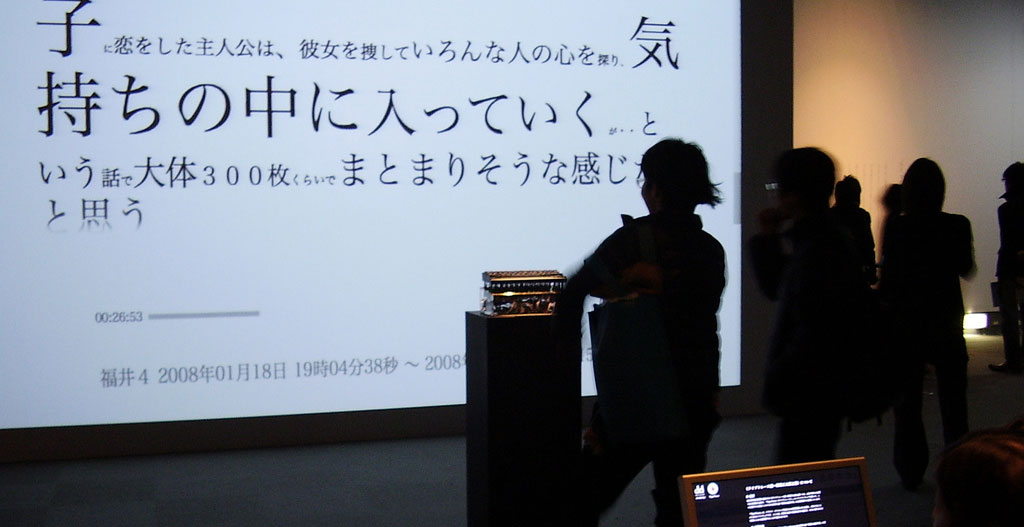今回カンバセーションズに初登場となるのは、企業のための広告や映像の撮影、建築、文芸、音楽、情報デザインなど領域を横断したドキュメントと共同作業を多く手がけている写真家の新津保建秀さん。そんな新津保さんがインタビュー相手に選んだのは、インターネット上における表現活動やコミュニケーション、コミュニティのあり方などに関する数々の著作で注目を集めるドミニク・チェンさん。スマートフォンアプリの開発などを行う株式会社ディヴィデュアルの設立メンバーでもあり、新たな視覚共有アプリをまもなくリリースするというドミニクさんに、新津保さんが聞きたいこととは?


ドミニクさんの少年時代はどんなものだったのですか?
ドミニク:81年生まれの僕にとって、幼い頃の遊びの記憶はまずファミコンなのですが、父親がオタクの走りのような人で、「PCロクハチ」と呼ばれていた日本産のマイコンが家にあるような環境だったんですね。マイコンを使って、当時プログラム雑誌に書かれていたコードを打ち込むと、音が出たり図形が動いたりして、自分が好きだったファミコンのゲームがつくられる過程を垣間見るような感覚がとても面白かったんです。また、8歳年上の兄の影響で、小学生の頃からエレクトロニカなどをよくわからないまま聴いたり、吉田戦車や相原コージなどの不条理系のマンガを読んだりしていました。ファミコンの影響が強かったからかビジュアルに対する関心が強く、近所に開館したばかりだった東京都写真美術館に自転車で行ったりしていましたし、祖父が満州で新聞記者をやっていたこともあり、形見としてもらったペンタックスで写真を撮ったりもしていました。また、父親が仕事でMACとスキャナーを使っていたので、10歳の頃には撮影した写真を取り込んで、Photoshopで合成したりもしていましたね。

当時の作品を見てみたいですね(笑)。中学・高校時代はどうだったんですか?
ドミニク:小学校を卒業してからは日本のフランス人学校に進んだのですが、父の転勤でフランスに行くことになり、高校生までは向こうで過ごしました。フランスやアメリカが面白いのは、オタクの人たちがとても社交的なところで、ゲームやアニメへの愛情をまったく隠そうとしないんですね。僕が学校をさぼって、パリのシャンゼリゼ通りにある映画館で「攻殻機動隊」を見て衝撃を受けたことをフランス人の友達に話すと、みんな凄く興奮するんです(笑)。オタク的な話題が広く共有できる気持ち良さというのがありましたね。あと、フランス人はお酒を飲むと余興的に政治談義をするようなところがあって、そういうフランスならではの文化の薫陶も受けました。フランスではあまりにバカをやりすぎて、高校2年の時に落第してしまったんですが、中・高校生の偶数年は落第しても自分の意志で進学ができるという不思議なシステムのおかげで救われました(笑)。
とはいえ、オタクと聞いて日本人がイメージするような人物像とは違って、ドミニクさんはどちらかというとリア充というか、コミュニケーション力がとても高いですよね。
ドミニク:いえ、全然高くないですよ! でも、アホな青春時代をフランスで過ごしたことで、身体的な感覚のようなものが多少培われたのかもしれません(笑)。先ほどもお話したように僕は81年生まれなのですが、コンピューターが特殊なものと捉えられていた少し上の世代とは違い、僕らは物心ついた頃からゲームのコントローラーを握っていて、ピクセルが動くとともに身体も反応するような感覚を持っているんですね。その後ネットが普及して、遠く離れた友達にメールが送れるようになったりして、なんだこの世界は!と(笑)。もっと下の世代になると、インターネットなども当たり前なんでしょうが、ちょうど僕らはネットやコンピュータに対する常識と驚きの間にいる世代で、身体とコンピューターが完全に一体化はしていないけど、情報のレイヤーなしでは生きていけないような感覚を持ち合わせているのかなと。大学院では、生命と情報の関係について研究したのですが、インターネットとの出会いには、18世紀の物理学者が顕微鏡によって新たな世界を発見したことに近い驚きがある気がしていて、それを客観的に記述したいという思いがあるんです。



僕が写真で世の中と関わりが持てるかもしれないと思うようになったきっかけは、あるフランス人アーティストとの出会いだったんですね。彼は、ドット絵でドローイングの歴史をトレースする作品などをつくっていたのですが、彼やその周辺の人たちと交流していくなかでフリーウェアのソフトや、ネットを介した海外の研究者との共同作業など、興味深いものを色々と目にして、写真を巡る環境もこれから変わっていくんだと考えるようになりました。彼は非常にマニアックな人である反面、そこに陥らないところがあって、ドミニクさんと似ていました。そうした感覚はどうして培われたと思いますか?
ドミニク:フランスにいた頃は、オンラインゲームにハマり過ぎて、大学に行けなくなったりした戦友がたくさんいたんですが(笑)、そういう方向は少し違うかなと思っていて。いまはデジタル的なリアリティの中だけで生きていこうと思えば、結構できてしまいますよね。ただ、それらを受け取っているのは自分の身体の感覚器であるわけで、そこが主客反転してしまうと、感覚そのものがおかしくなってしまうんじゃないかと。オンラインゲームにしても、完全に向こう側に行ってしまうとそれは異質の体験になってしまい、いま自分が感じている楽しさみたいなものを研ぎ澄まされた感覚で味わえなくなってしまうんじゃないかと思うんです。

僕の5才の娘はいまゲームが大好なのですが、没入し過ぎている時はとこっち側に連れて来ます(笑)。
ドミニク:要はバランス感覚みたいなものだと思うのですが、自分にそれが植え付けられたのは、フランスの教育システムによるところが大きい気がします。学校の授業で、クラス全員がゾンビに一人ずつ殺されていくという話を書いたことがあったんですが、そんな残酷な話を書くなと怒られることはなく、書き方の稚拙さや、物語の構造について指摘されたり、評価されたりします。要は、何を思うのかという部分は個人の自由なんですね。また、フランスの哲学の試験というのは、たとえば「戦争は悪か?」という一行の問題に対して、2時間通して答えを書いていくようなものなんです。もちろん、自分の意見を導くためのメソッドはあるのですが、どんな答えであろうと、どこまで自分に嘘をつかず、強度のあることを言えるかが何よりも重要。小学生の頃はファミコンやマンガ、写真や映画などのビジュアルに影響を受けたと言いましたが、高校・大学ぐらいの時期には、言葉の面白さというものに衝撃を受けました。
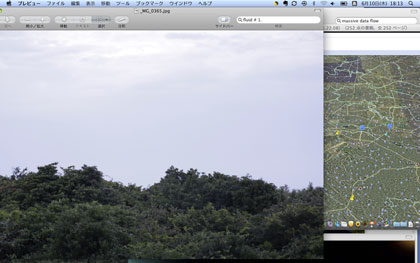
僕が個人的に魅かれる写真家には、写真を専攻したからということで写真家になった人よりも、まったく別のことを経て写真に至った人の方が多いのですが、ドミニクさんの場合も、あらかじめあった器に自己を合わせていく感じでなく、その時々の選択が現在の作業へ自然に繋がっている気がしますね。
ドミニク:僕には常々、世界の豊穣さを感じたいという思いがあるんです。デジタルかアナログか、ビジュアルか言葉かということは、そのための経路にしか過ぎず、どちらも味わい深いものですし、驚嘆すべきことが世の中にはたくさんある。僕はこんな名前だし、国籍はフランスですが、文化的な影響は日本からのものが大きいし、さらに台湾やベトナムの血や文化も入っています。これは僕だけではなく、ハーフの人たちはみんな同じだと思うのですが、特定のコミュニティに対する帰属意識みたいなものが持ちにくいんですね。その中でどうにかバランスを保とうとするために、生々しさやリアリティみたいなものを追求しているところがあるのかもしれません。



ドミニクさんがインターネットに触れるようになったのはいつ頃からですか?
ドミニク:大学はUCLAのデザイン系学科に進んだのですが、当時はちょうどグーグルなどが出てきて、ワークステーションにはPhotoshopやIllustratorが完備されていたにも関わらず、みんなのお目当てはインターネットでした。インターネットを通して、世界中の映像や音楽に触れて、世界の面白さを改めて感じられたし、L.A.で開催され、衝撃を受けた『SUPER FLAT』展のキュレーションをしていた村上隆さんが当時、「芸術道場」というネット掲示板を運営していたんですね。L.A.の学生寮の片隅から、「芸術とゲーム」「芸術とマンガ」などのお題に対して、自分の思いの丈をぶつけていたのですが、それが面白がられて、最高段位を頂くことができ、芸術道場師範代の楠見清さんのお声がけで『美術手帖』で展評や論考などを書かせて頂くようになったんです。現代美術には、日常生活では遭遇できないようなつくり手の思考がドロッと出ているような生々しさがあるし、色んなものがゴチャゴチャしながらも歴史とルールがしっかりあって、混沌と秩序の間で1mmでも人類を前に進めていこうとしている感じがとても面白かったんです。

ドミニクさんの書かれたテキストは色んなところで目にしていて、シャープな文体もとても印象的だったのですが、こうしてお話を聞いていると、色々なことが腑に落ちてきました(笑)。
ドミニク:現代美術の世界でひとつ不満があったのは、なかなかコンピューターの話をできる人がいないということでした。ファミコンから始まり、ネットに連なっていくコンピューターの生々しさみたいなものがあったのですが、最近は少しずつ変わってきているとはいえ、当時はコンピューターやメディアアートは、現代美術とは別物として扱われていました。UCLAにいた周りの連中なんかは、光センサーをつかってDJソフトをハックするようなことをしていたし、ステラークという有名なオーストラリア人のメディアアーティストは、身体にIPアドレスを割り当て、ライブを見ている人がアドレスを入力すると特定の部位に電流が流れるというパフォーマンスなどをしていて、そういうものがとてもリアルに感じていました。そこから徐々にコンピューターメディア周りのアートフォームに興味を持ち、2003年に大学を卒用した後にICCに就職しました。

その後会社を設立し、現在はアプリ開発などを行っていますが、そこにはどんな経緯があったのですか?
ドミニク:2005年頃から、ホワイトキューブの中の狂気よりも、シリコンバレーの狂気の方が面白いと感じるようになったんです。いまでは都市伝説的な話になっていますが、ドイツのART+COMというアート集団が、90年代末に現在のGoogle Earthのような作品をつくったことがあって、その展示を見て触発された人が、その後実際にGoogle Earthをつくったという話なんです。その真偽は別として、メディアアート界がデモンストレーション的な作品で興奮していたものが、グーグルやフェイスブックによって社会実装されてしまったと考えると、個人の狂気よりも、むしろ情報社会の方が狂気じみた進歩をしているんじゃないかと。この生々しさをキープするためには、自分もそっちに行く必要があるんじゃないかと考えるようになり、その頃に意気投合したメディアアーティストの遠藤拓己と一緒に会社をつくったんです。僕にはずっと、ピュアリー・デジタルでも、ピュアリー・フィジカルでもない宙ぶらりんのリアリティがあって、常にそれを肌で感じられる場所に身を投じてきている気がします。


会社を立ち上げてからはどんなことをされてきたのですか?
ドミニク:最初は、一緒に会社を立ち上げた遠藤がもともとプロトタイプをつくっていた「TypeTrace」というアプリのウェブ版を開発していたのですが、その途中で夏休みの課題的に、うちのスーパークリエイターの山本興一を中心につくった「リグレト」というアプリがあって、1週間で1万人くらいの人たちがユーザー登録してくれたんですね。それからはこちらに集中しようということになり、3、4年ほどコミュニティの運営をメインに行ってきていますが、メディアアートの作品をつくることとはまったくプロセスが違うんですね。カスタマーサポートに対応し続けたり、自分もデータベースの中に入って検証してはアルゴリズムを変えたりと、ありとあらゆることをしています。アートというのは、基本的にあるビジョンに基づいて完成したものを提示する場合がほとんどですが、プロダクトやアプリケーションは、自分たちの計画からはみ出ていくところが面白いんです。逆に作り手の計画通りに使われるようなものは、プロダクトとしてよくできていると言えるかもしれませんが、そこから化けることはありません。意図されない使われ方をすることを、意図的に考えていくという矛盾が面白いんです。

写真を撮影する時も、現場のすべてをコントロールしようとすると上手く回らないんですね。最初に決めたことにこだわってしまうとどんどん振幅がなくなり、出来上がるものも死んでしまう。逆に、その場で起きている偶発的なことに対して、波乗りをしていくような感覚で身を開いていくと、予想していなかったものが立ち上がってきます。
ドミニク:完全に制御したり、把握しようとする発想自体に一種の傲慢さがあるんじゃないかという考え方にリアリティを感じていて、色々研究していくと、ノーバート・ウィーナーという数学者が20世紀半ばに書いた『サイバネティックス』という本に出会いました。彼は、弾道ミサイルの計算や義足の設計などをしていた天才的な数学者なんですが、同時代のジョン・フォン・ノイマンという人がつくったCPU処理系統がある現代のコンピューターの構造やゲーム理論を批判しているんですね。ノイマンという人は、指示と制御による世界を目指していたのですが、それは世界の複雑さを切り落としていくことにもなりかねない。ウィーナーの考え方は違っていて、その観点を発展させていくと、新津保さんがおっしゃるように、システムの構成要素に指示するのではなく、各自が自律的に動けるように動きを整合させていくという有機的な方法につながっていったんです。

2011年にある講座で、1年間にわたって写真の講評をする機会を頂いたのですが、その時に意識したのは、作家性を偏重しないで、写真の可能性を探りたいということでした。作家性に基づいて凄く強度のあるものを撮って作品とするのではなく、そこからこぼれてしまうものの可能性が探れたらと考えていました。そういう意味で、ドミニクさんの今回のアプリの背後にある考え方には色んなヒントがあるような気がしています。
ドミニク:僕には変なこだわりがあって、物事がフェアかどうかということを異常に気にするんです。そういう意味では、特権的なものというのはフェアじゃないと思いますし、そういうものはつまらない。例えば、芸術や哲学の世界には、「この人がつくった作品だ」とか「最初に考えたコイツが偉い」みたいな風潮がありますよね。でも、偉いものがたくさんある文化はつまらないし、それを破壊する動きが出てくるのが健全なことで、同じようなことがいま情報の世界においても起こっていると思います。いまだにプログラマーは機械的に考える天才だという風潮がありますが、全然そんな特権的なことではないし、非常に人間的な感性こそが重要になってきている。いま僕たちがつくっているものにしても、「作者」や「作品」という概念はありません。そもそもユーザーが来てくれないとドライブしないという状況の中で、会話をしながら自然に流れていくようなリアリティというものをつくりたいんです。
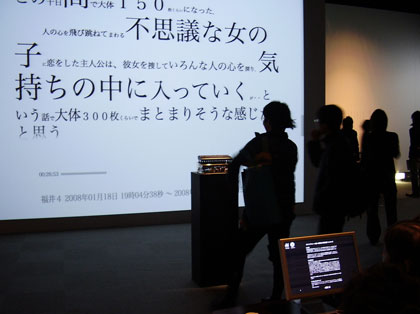


先日、荒神明香さんらによるユニット「目(め)」の新作展、その後に『バルテュス』展を見る機会がありました。その少し後に、ドミニクさんたちが開発中のアプリにテストユーザーとして関わらせてもらって、このアプリを日々使っていくなかで、表現におけるフレーミングの意味を改めて考えていました。
ドミニク:いま作っているものは、言葉よりも速く、たくさん伝わるというコンセプトで、クローズドなグループのメンバー同士がまるで同じ一台のカメラを使っているかのように、互いに撮影した写真が手元に保存される視覚共有アプリです。このアプリのきっかけとなったのが、僕と妻のあいだで娘が生まれてから写真を撮る機会が一気に増えて、10ヶ月あたりでふたりが撮った写真が合計で8,000枚ほど溜まっていたのですが、それを1カ所に集めるのがかなり大変だったんですね。やっぱりそれぞれの視点で撮った娘の写真を見たいわけですよ(笑)。DropboxやAppleのPhoto Streamといったツールもありますが、ITに詳しくない人にはまだまだ使いづらかったりするんです。そこで、僕と奥さんがそれぞれのiPhoneで撮った写真がバーチャルに同じ場所に入っていって、いちいち送信する必要なく記憶を保存できるものがあるといいなぁと。
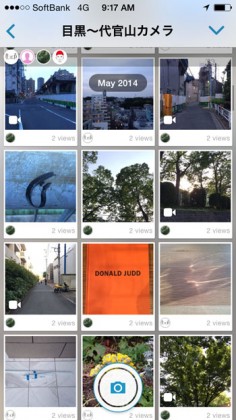
実際にこのアプリを使ってみて、自分が知っている誰かに対して写真を撮るということは、普段のように不特定多数の人に向けて撮ることとはだいぶ感覚が違うんだと感じました。また、僕らはいま3人のグループで使用していますが、3人の視点によってつくられた目に見えないフレームみたいなものがあって、それを通して世界を見ることで、自分にはない感覚が立ち上がってくるところがあるんです。このアプリは色々な可能性を秘めていると感じるし、多くの人に使ってほしいと思います。
ドミニク:はい、アプリを作り始めてからすぐに、これは家族に限定されない、多様なシチュエーションで広く使ってもらえる可能性があることに気付きました。例えば、新津保さんたちとのグループでのやり取りでは、送られてきた写真に対して、言葉ではなく写真で返事をしていくような、純粋にビジュアル感覚でコミュニケーションを行うのがすごく面白いですね。このアプリには、新津保さんがおっしゃるように、不特定多数の人が見るFacebookやInstagram、Twitterみたいなパブリックなネットサービスでは自分を飾り立ててしまうことで削ぎ落とされてしまう、ある種の生々しい官能的な感覚があります。LINEでは言葉でコミュニケーションが始まり、スタンプや写真が付随しますが、 このアプリでは逆で、写真や動画がコミュニケーションの主体で、言葉はキャプションやコメントとして付随するものなんですね。特定の相手と日常的に写真を撮り合うことで、言葉がだんだん不要になってくるプロセスがとても気持ち良いんです。このアプリを介して多くの人の間で非言語的な親密さが伝播していけばうれしいですね。
ひとりの人が世の中に投げかけた創作物が、数年かけて色んな人たちに影響を及ぼし、そこに込められた思想が社会に広がっていくということがあります。かつては思想家や芸術家らが担ってきた役割だったのかもしれませんが、現在は、研究者や独創的なビジョンを持った法人もこれに当たるんじゃないかなと思うことがあります。
ドミニク:そうですね。僕たちが目指しているのは、コンピューターに人間が合わせていく世界ではなく、人間の自然に近いコンピューターをつくることなんです。このアプリもそうですが、人間の身体的な感覚とつながっているテクノロジーというのが自分たちの目指している方向性なんです。先日、(スティーヴン・)ホーキング博士がインタビューに答えていたのですが、いま人類にとって最大の危険は人工知能だと。人間が理解することのできない人工知能によって、情報社会に生きる人間の存在が規定され始めているというんですね。僕としては、人間が人間として鋭敏な知覚で面白いものに接し続けられるような情報社会をつくりたいですし、そのためにもプログラミングというものが脱幻想化されて、より多くの人に情報サービスをつくることに参加してほしいという思いがあります。 ビジネスマンとして教育を受けた人なら、いかに効率よくプロダクトをリリースして、利益を上げるかということを第一に考えると思いますが、それは理念を社会実装していくことでもちろん重要なことです。でも、それがすべてではないですし、情報の力が過多に喧伝される今日だからこそ、時には非合理的だったり情感的だったりする人間世界の豊穣さや深さから新しいコミュニケーションの在り方を考えていきたいんです。
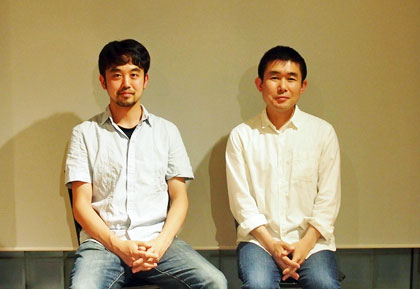


ポートレートを撮る時、その人の親しい人を2人ほど連れてきてもらって、その3人でいる空気の中で撮影すると、和やかな空気が流れ、自然な表情になることが多いです。そんなわけで、ドミニクさんより著者近影の撮影オファーを頂いた時、親しい方をおふたり連れてきてくださいとお願いしました。彼は、奥さんと娘さんと来てくれ、撮影はとても和やかに進みました。(ガールフレンドを2人連れて来る人もいるので、えらい違いです。)
撮影の後、彼の会社が開発するアプリの試作版を見せてくれて、開発のモチベーションを話してくれました。それは、生まれたばかりの娘さんの写真をドミニクさんと奥さんのそれぞれのご家族と共有することへの欲求から始まったということでしたが、子供の誕生を契機に生まれた絵画や音楽の話は聞いたことがあるけど、アプリケーションの話は初めて聞いたのでとても印象に残っています。
今年の春、このアプリのテスト版をいただき、これを使って僕らの共通の友人3人で写真を撮影・共有していく過程で、これまで漠然と見ていたものが明瞭な輪郭を持って立ち上がってくる瞬間が何度となくありました。その時、このアプリケーションはドミニクさんがこれまで考えてきたことが、とても開かれた形で社会へ向けて実践されていることを感じました。もしかしたら、新しい経験の共有方法をつくり出したのではないか、とも。
今回はこれまでの活動を裏付ける価値観の一端を伺えたように思います。ありがとうございました。