

名和さんとは同じ大学で教えている立場でありながら、学部も違いますし、これまで意外と接点がありませんでした。僕はデジタル領域のデザインが主な仕事ですが、名和さんは現代アートの分野で活躍をされていて活動領域も異なりますが、世界で最も注目すべきアーティストのひとりだと思っています。今日は、個人的な興味のもと、色々お聞きできればと考えています。今回は、「育む」という難しいテーマを与えられているのですが(笑)、本来つくり手というのは、自分も含めずっとつくっていたいという思いがあると思うのですが、その中で教育の現場に関わられている理由は何なのでしょうか?
名和:いま僕は芸術学部美術工芸学科で教えているのですが、大学に総合造形という新しいコースをつくる際に、カリキュラムや入試の問題などの計画をしてほしいという話を頂いたんですね。もともと学生の頃から、造形教育に対してもっとこうであれば良いのにという思いがあったので、この機会にそれを実現できるのではないかと。スケジュールの都合などもあり、今年から大学に来られるのは2週間に一度と以前より少なくなってしまいましたが、教え子が徐々に現代美術のシーンで作家として活躍し始めていて、やはりやっていて良かったなと感じています。大学を出てしまえばもう先生と学生の関係ではなく、同じフィールドで戦う仲間になるわけで、そういう存在が増えていくのはうれしいですし、現代美術シーン自体が盛り上がらなければ、自分もやっていけないのではないかという恐怖があるので、こうした場を通じて、全体の底上げをしていく必要性を感じています。

大学で教えられる前から教育というものには興味を持っていたのですか?
名和:はい。両親が教師だったということもあるのですが、博士課程で教育理論や造形教育の研究をしていて、論文も書こうとしていました。また、博士課程の時から京都芸大の非常勤で彫刻を2年間教えたり、その後も京都精華大で版画を、京都造形では染織をそれぞれ非常勤で教えていました。また、大学院生の頃には自宅近くの文化センターのようなところで、名和美術教室というものを自主的に開き、3歳くらいから50~60代くらいの方までと一緒に造形をやっていました。また、(ルドルフ・)シュタイナーの造形教育の考え方などにも触れていくなかで、教育というものはずっと興味の対象としてありました。
この大学では、学生たちとULTRA SANDWICH PROJECTというものをやられていますよね。今日会場に来ている学生の中でも関わった経験がある人が結構いるようですが、このプロジェクトはどのような意識で取り組んでいるんですか?
名和:すでに5年程続けていて、合計百数十名の学生が参加しているのですが、このプロジェクトでは、僕の作品づくりはもちろん、学生がいるからこそ受けられるプロジェクトにも積極的に取り組んでいます。例えば現在は、あるきっかけからジャルジャルというお笑い芸人がSANDWICHに来て生放送を撮るということになったので、ULTRA SANDWICH PROJECTのメンバーでジャルジャル研究をして、彼らにネタを提案するということをする予定です(笑)。その他にもミュージックビデオの仕事や、最近では尾道にできたホテルのエントランスのアートワークの企画、制作、設置を学生主導で行いました。せっかくやるからには学生のプロジェクトになってほしいと考えていますし、ある種教育機関のような体制の中で、SANDWICHでしか起こりえないことを積極的に支援していきたいと考えています。



いまお話に出たSANDWICHは、クリエイティブプラットフォームと定義されていますが、アートのみならず建築やインテリア、プロダクトなどにまで領域を広げていますよね。なぜそのような動きをされているのか、とても気になるところです。
名和:最初から明確な青写真があったわけではなく、どんな立場の人でも入ってこられるオープンなクリエイティブプラットフォームという最初のコンセプトだけを貫き、自然といまのような形に広がってきているという感じです。SANDWICHを始める前は、閉じられた個人スタジオのようなものをつくっていたのですが、徐々にスタッフが増えたことから、スタジオのシステムを強化する必要性を感じるようになりました。ちょうどその頃にヨーロッパでいくつか個展の予定などがあったので、スタッフを連れて1ヶ月ほどヨーロッパを回り、そこで色々なスタジオなどを見学させてもらったんですね。その時に訪問したスペインのマドリッドにあるStudio BANANAというところでは、計40人前後のアーティスト、建築家、写真家などさまざまな立場の人たちがスタジオをシェアしていて、カンファレンスやワークショップなどのプログラムも共同で運営していたんです。僕も学生の頃から作品制作の際に建築家や溶接工場の人、アクリル職人さんなどにお世話になることがあったので、何かひとつのプロジェクトがある時に、そこにいるクリエイターだけですべてを完結できてしまうという体制が理想的だと感じ、徐々にSANDWICHの構想が膨らんでいきました。

もともと名和さんは表現できるものはなんでもつくりたいという欲求が強そうですね。
名和:そうですね。彫刻というジャンルにこだわっているわけではなく、彫刻的な感覚を色んな方向で表現できればと考えています。大学の時は油絵作家を目指していたし、写真や映画も撮りたいと思っていました。街中を歩いていても建築を見たら自分で変えたくなってしまうし、ファッションなどにしてもこういうデザインなら良いのにというのが見えてくると、直接やりたくなるんです。常にそういう視点で見てしまうところがありますね。

名和さんの作品というのは、制作のプロセスでデジタル技術を用い、それを彫刻というアナログの形でアウトプットされていて、先日伺ったアートバーゼル香港の出品作の中でも異質な印象を受けました。美大生でもデジタル領域にアレルギーを示す子は少なくないですが、名和さんはアーティストとして、通常美大などでは教えてもらえないような最新のデジタル技術から哲学、医学などの学問まで、幅広い知識を得られているように感じます。おそらくそれは自ら興味を持って、ある種領域を逸脱していかないと手に入らない知識・ノウハウだと思うのですが、名和さんはそれらをどのように得ていったのですか?
名和:コンピューターやデジタル技術などに関しては、そんなに使いこなしているわけではないんです。でも、これだけデジタルツールに親しんでいる現代の感覚というのは、必ず作品に反映されていくものだと思いますし、いまの世の中にどんな技術や考え方があって、それをどのように使うと表現の可能性が広げられるだろうということを考えながら、常に制作に取り組んでいます。また、子供の頃から変わっていないのですが、好奇心が強く、それをひたすら探求しているだけなのだとも思います。知りたいことがあればそれが分かるまで調べますし、できる限り自ら実践するようにしています。仮に実践することが難しいような場合でも、頭の中では常に多くの思考実験のようなことをしていて、その中でたまたま実現したものが自分の作品なんです。学校で習うことが、そのような好奇心が得られるきっかけになればいいのではないかとか考えています。



名和さんの著書を読むと、哲学書なども色々読まれていて、そこから着想を得て作品のコンセプトがつくられることもあるようですね。例えば、先に話が出た(ルドルフ・)シュタイナーとの出合いというのは、名和さんが自ら興味を持った結果なのでしょうか、それとも教育を受けるなかできっかけが与えられたのでしょうか?
名和:シュタイナーに関しては、たしか18歳の誕生日の時に、姉から本をプレゼントしてもらったのがきっかけだと思います。姉も美大を出ているのですが、その頃哲学などにも傾倒していたんです。でも、それを高校時代にもらった僕は、しばらく受け付けずに読まなかったんですね。その後何年も経ってから、何かをたどっているうちにシュタイナーに興味が出てきて、読むようになりました。

インキュベーションではないですが、本をもらってからしばらくして卵が孵化していった感じですね。
名和:学部時代はどんな本を読めばいいのかわからず、純文学を読みあさった時期などもありました。大学院に進み、論文などを書くにあたり、自分の考えが言葉にならないもどかしさを感じるようになったんです。当時、日本の宗教を研究テーマにしていたのですが、次第に世界の宗教や民族なども調べるようになる過程で、自分が持っている感性にはどういう由来があるのかに興味を持つようになったんですね。そうすると、中世の宗教美術などもリサーチの対象になってくるし、その過程で建築と美術が同時に育ってきた時代があったこともわかりました。また、東洋に目を向けると、戦後の日本のポストモダンと呼ばれるような時代には、さまざまな文化がないまぜになり、ランダムにクリエーションが生まれているように見えてきて、その糸をたどっていきたいと思うようになりました。このように自分の色々な興味と向き合っていくなかで、シュタイナーの造形教育や人智学も自分のインスピレーションソースになっていきました。
名和さんはロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)にも交換留学で行かれていますよね。作品のつくり方やコンセプトなどに対して、常に新しいアプローチで挑戦を続けている教育機関という印象があるのですが、ここでの経験も大きかったのですか?
名和:そうですね。それまで京都芸大の閉鎖的とも言える環境の中で、概念をねちねち考え込むような生活をしていましたが、ロンドンに行くと、情報量ははるかに多く、アーティストが社会的な地位を築き、いまという時代に対して戦っているように見えました。そういうことができるなら自分もやりたいと思いましたし、自分の考えたことをアウトプットした時に、それを受け止めてくれる場があるんだということを感じました。また、RCAにはまさにしのぎを削っている雰囲気があるんですね。人生をかけて勝負しようとしている人たちが世界中から集まっているから非常に緊張感があります。そこからのし上がってくためにはやはり相当タフじゃないといけないわけです。そうした人たちが戦っているフィールドに乗り込まないといけないんだということを思い知った時期でした。自分の中のハードルを上げ切って帰国をして、それからは周りの友人も驚くほど、創作活動をベースにした生活のサイクルが始まり、それが現在も続いているという感じです。
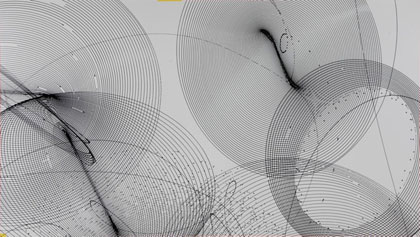


「見たこともない表皮をつくる」という名和さんの作品の核となる部分が築かれていったのはいつ頃なのですか?
名和:留学をしている時に、ヨーロッパの宗教芸術や現代美術を見て回ったのですが、その過程で自己表現というものに固執する考え方がなくなったんですね。表現というものが世界中で行われているなかで、いまという時代にどんなクリエーションが起こり得るのかを考えた時に、極端に言うと、わざわざ自分自身の内面を表現のテーマにしなくてもいいんじゃないかと思うようになりました。それよりも開かれた表現によって、いかに見る人との接続点や接続面を作品に持ち込めるかということを意識するようになりました。そこから、新しいマテリアル、テクスチャ、インターフェースを求めて、言葉やコンテクストを越えて感覚が接続されるというテーマを掘り下げていくことで、強い彫刻表現ができるようになるのではないかと考えるようになりました。そのコンセプトを実践していったのが大学院時代の2年間でした。

名和さんは大学院まで出ていますが、大学教育というものは名和さんの活動や作品に対してどのような影響を与えたと感じていますか?
名和:大学を卒業する時には、色んな人から大学院には行かなくていいと言われたりしてかなり迷ったのですが、いま振り返ってみて、博士課程の3年間はやって良かったと思っています。当時、田中泯さんの舞台の手伝いなどもしていて、泯さんからも大学にいつまでいるんだ、社会に出て戦えなどと言われたのですが、僕は彫刻をやっていたので大学のようなスペースや機材を他で手に入れることは難しかったですし、3年間粘ってつくり続けたことで、自分の作品の理論や体系を構築していくことができました。また、博士課程の頃には積極的に作品発表もしていたのですが、そうした実践の中で学べたということが非常に大きかったと感じています。当時は、大阪のギャラリーで毎年個展をしていて、ギャラリーのディレクターと喧嘩するほど意見交換を続けながら作品をつくっていったのですが、そこには大学の先生が言うこととはまったく違うシビアな観点からの意見もたくさんありました。悔しくて寝れないようなこともしょっちゅうありましたが、当時の経験はとても重要だったと思います。その頃に学んだことがベースとなり、当時は技術的、予算的な理由でつくれなかったものを、この10年の間で少しずつ実現している感じです。
名和さんの作品の理論や体系というのは、頭がおかしくなるくらい考え抜いた末に残ってきたものなのだと思います。最後に、京都に学びに来ている学生たちに向けて、何かメッセージを残して頂けますか?
名和:この大学には色々な先生が来ているし、外部からの刺激がたくさん入ってくると思いますが、その情報量に負けないようにすることが大切です。飽和状態のなかでお腹いっぱいになった気になって大学時代をやり過ごしてしまうのは、もったいないことです。自分自身がこの1年、1ヶ月で何を得るのかを明確に意識することが大事です。それは知識でも経験でもいいし、何かが身体に染みこんでくるような環境でもいいのですが、自分のハードルや価値基準を高く保てる環境や人とのつながりを発見できると良いと思います。また、人の中にはクリエーションの化け物のようなものが潜んでいて、それは時に獰猛で、何をしでかすかわからないようなエネルギーを持っています。その存在に気づき、しっかり栄養を与えて育てていくことで、食欲や性欲、睡眠欲に勝るほどの制作欲という、クリエーションに対する欲望を膨らませていくことができれば、もの凄いことになるはずです。周りのペースに合わせる必要はありません。自分が世界一になってやろうというくらいの野心を持ってがんばってほしいですね。そういう人がこの大学からゴロゴロ出てくるようになるといいなと思っています。



